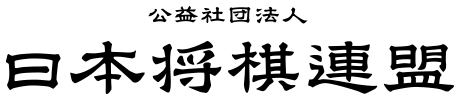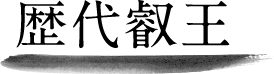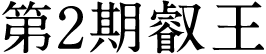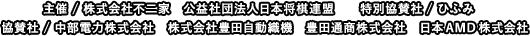




- 佐藤 康光 日本将棋連盟会長
- 1969年、京都府生まれ。田中魁秀九段門下。1987年、四段(プロ入り)。1998年、九段。タイトル戦登場37回、獲得は名人2期、棋聖6期など計13期で、永世棋聖の資格を持つ。読みの深さから「1秒間に1億と3手読む」「緻密流」と言われる。2017年2月から日本将棋連盟会長を務める。
タイトル戦の10時と15時に設定される「おやつ」タイム。
五番勝負の対局で、
不二家が提供した「おやつ」を紹介します。
第3局






第2局






第1局







- お菓子BOX紹介
- 叡王戦限定で提供される「ペコちゃんお菓子BOX」の中身を公開。
勝負の一手を後押しするお菓子にも注目です!
対局篇・棋士篇は村中秀史七段に
答えていただきました。
- 村中 秀史
- 高柳敏夫名誉九段門下。2004年、四段昇段。2019年七段。東京都北区出身。
ブログ、Twitter、YouTubeチャンネルで情報発信するなど、精力的に活動している。
祖父から教わったことを契機に将棋を好きになり、両親に連れられ高柳将棋道場に入門。末弟子として12歳で奨励会入りし、23歳で四段(三段リーグ1位14勝4敗)となった。


将棋の起源は、古代インドのチャトランガというゲームにあるという説が最有力です。ヨーロッパやアジアの各地に広がり、西洋ではチェス、中国ではシャンチー、朝鮮半島ではチャンギ、タイではマークルック、そして日本では将棋に発展したと考えられています。将棋がいつ誕生したのかはっきり分かっていませんが、1993年に奈良県の興福寺境内から発掘された駒が最古といわれています。(天喜6年=1058年と書かれた木簡が出土しました)

現在タイトル戦は、竜王戦、名人戦、王位戦、王座戦、棋王戦、叡王戦、王将戦、棋聖戦の8つがあります。タイトル戦にはタイトル保持者がおり、約1年のトーナメント戦もしくはリーグ戦を通してタイトル保持者への挑戦者を決めます。その後、タイトル保持者と挑戦者の間で七番勝負もしくは五番勝負を行い、勝ち越したほうがタイトル保持者となります。
棋士の肩書きは通常は段位となりますが、タイトル保持者の場合は、「○○叡王」というようにタイトル名が肩書きとなります。また、竜王戦と順位戦(名人戦の予選)は、それぞれクラスとランキングがあり、その期の成績によって成績上位者は昇級、成績下位者は降級するなど、挑戦権争い以外にも厳しい戦いがあります。

永世称号は、そのタイトルを規定回数獲得したときに得られる資格です。永世称号は、原則として引退後に名乗ることになりますが、相当数のタイトルを獲得または防衛しなければならず、永世称号を獲得することは、強い棋士の証となります。

八大タイトル戦の番勝負では、全国各地のホテル・旅館・神社仏閣等で対局を行っています。
開催地には多くの将棋ファンが訪れます。また、新聞等のメディアで取り上げられることで、地域の魅力発信に寄与しています。

中央に座っている人は「立会人」です。タイトル戦の対局では、棋士が立会人を務めています。対局開始の合図や、対局中に何か問題が生じた際に適切に対処するという大切なお仕事です。

平手戦における先手と後手は「振り駒」によって決定します。公式戦では、記録係が上座の対局者の歩を5枚振ります。振り駒の結果、「歩」が多く出たら駒を振った方(上座)が先手、「と金」が多く出たらもう一方(下座)が先手になります。

対局者の持時間は各棋戦によって異なり、計測方式は1分未満の考慮時間を切り捨てる方式と、考慮時間を秒単位で加算する方式があります。1分未満の考慮時間を切り捨てる方式では、持時間を使い切る1分前(残り1分)より秒読みとなり、使い切った場合は負けとなります。考慮時間を秒単位で加算する方式では、持時間を使い切ってから秒読みとなります。
秒読みは記録係が行い、1分将棋の場合は「30秒・40秒・50秒・1・2・3・4・5・6・7・8・9・10」と、秒を読みます。最後の「10」を読まれた対局者は負けとなります。

終局後、お互いに対局を振り返って感想を述べ合うことを感想戦と言います。お互いの健闘をたたえ、さらなる棋力向上のために対局を振り返って、複雑な変化手順を検討したりします。なかなか納得のいく結論が出ない場合には、長時間になることもあります。

現在、現役・引退あわせて約230名の棋士がいます。現在は男性しかおりませんが、奨励会を卒業して四段になれば性別を問わず棋士になります。また、それと別に、女性のみで構成された女流棋士という制度もあります。研修会で規定の成績を挙げることによって、女流棋士になります。
女流棋士になると、女流公式戦に出ることができます。女流公式戦は8つの女流タイトル戦と1つの女流優勝棋戦があります。

プロ棋士の公式戦では先手番の勝率がやや高い傾向にあります。(2020年度は約3500局の対局結果で先手番の勝率が52~53%)先手番はやはり一手早く指せる事で戦いの主導権を握りやすい事が大きな要因に考えられます。プロ棋士は「できれば先手番で指したい」と全員が思っているのではないでしょうか。リーグ戦などあらかじめ先手後手が決まっている対局以外では、当日の振り駒によって手番が決まります。もちろん確率は五分なのですが、結果的に後手が続いてしまう事もあります。5局くらい続くとどうしても「さすがにそろそろ先手が欲しいな」と思ってしまいますね。

居飛車は最初の形(初形)から飛車を真ん中から右で使う作戦の総称です。逆に振り飛車は真ん中から左側に飛車を転戦させて活用します。ちなみに真ん中(5筋)で使うと中飛車戦法という振り飛車になります。プロ棋士では居飛車党(居飛車を主戦として採用する棋士)の方が人数が多いですね。
昔は振り飛車戦法は比較的受け身の作戦と言われていましたが、近年は攻撃的な振り飛車も増えてきました。それでも居飛車の将棋に比べるとじっくりとした進行になりやすいので、玉をしっかり囲って戦いたい方や、受けが好きな方に振り飛車は向いていると思います。

序盤戦=作戦の分岐と決定(居飛車、振り飛車など)、玉を囲う(守りの布陣の整備)、攻撃の準備など。
中盤戦=お互いの駒がぶつかって本格的な戦いに突入。目安としては駒台に複数の駒が乗ったら中盤戦です。
終盤戦=相手本陣への攻め合い。中盤戦と比べると玉近辺への直接的な攻めが多くなります。
手筋=駒を効率よく使うためのテクニックの総称で、主に部分的なものを言います。「ここは銀を引くのが手筋」といった使い方です。
駒得=相手の駒を取ったり、より価値の高い(強い)駒との交換になると『駒得』になります。
詰めろ=王手はかかっていないが、次に相手の玉を詰ませる状態。ただし『必死』と違ってまだ受ける事ができます。「詰めろをかける」「後手玉は詰めろ」「詰めろを受けた(次の詰みを防いだ)」といった使い方をします。
必死=詰めろと同じく王手はかかっていないが次に詰ます事ができる状況。詰めろと違ってそれを防ぐ事ができない。『詰めろ』の上位互換のようなイメージです。「自玉には必死がかかっているので、(この手番で)敵玉を詰ますしかない」といった使い方をする。
寄り筋=玉が詰んだり、必死がかかるといった状況を言います。「金を取って寄り筋に入った」といった使い方です。
一手一手の寄り=受けても状況が悪くなる一方の時に使います。「金を受けても歩を成られて一手一手の寄り」といった使い方です。「寄り筋に入った」と意味は近いです。

私もですが自分の指した対局をAIで解析する棋士は多いと思います。研究の段階では課題となっている局面でAIがどのような判断をするのかといった使い方をしています。どちらが優位かここでどのような手があるのかといった一つの指針を示してくれるのでより深く正確な研究の助けになります。
AIも時間をかけたほうがより正確な判断を下します。ですので中継で数値が変化する事があるのはAIが手を深く読んだ結果で新しい手を発見したりして評価が変わるからです。

まずは初心者向けの将棋の本を読んでルールを覚えましょう。ネットの動画などもありますが駒の動かし方などの基本的な部分は本で学んだ方が良いと思います。ルールを覚えたらコンピューターやスマホのアプリで実際に指してみましょう。最初は勝てないですが駒を動かしてみる事が大事です。結果を気にせずにやってみましょう。対局をやっていくうちに駒の動かし方はマスターできると思います。

将棋は非常に奥深いゲームです。そして勝敗における運の要素が少ないので、基本的には弱者が強者に勝つ事は難しいです。実力差がある相手と対局をする時は上位者の一部の駒を取り除いた「駒落ち戦」で戦いましょう。例えば「飛車落ち」であれば上位者の攻撃力を削ぐ事ができます。それでも勝てなければ「二枚落ち(飛車と角を取り除く)」といったようにハンデを調整して対局を楽しんでいただければと思います。

将棋の決着は対局者に委ねられています。自由に自軍の駒を使って指揮を執りますが、その結果には自分が責任を取ります。 対局開始の「お願いします」と終局時の「負けました」そして「ありがとうございました」は将棋の大切なマナーです。
将棋は、まだ自分の玉が詰んでいなくても駒をたくさん取られるなどして戦力不足で勝機がなくなる事もあります。飛車などの大駒を取られて戦意を喪失する事もあるでしょう。敗戦は悔しいですが相手の実力を認めてしっかりと「負けました」と言いましょう。

将棋の符号は盤における住所です。升目の縦を段(だん)、横を筋(すじ)と言います。段は上から一、二、三…という漢数字、筋は右から1、2、3…と算用数字を用います。例えば一番右上の升目は「1一」に、一番左下が「9九」になります。初期配置で言えば香車がいるところですね。符号だけで場所を判断するのはなかなか難しい技術です。苦手な方は、例えば初期配置で飛車がいるところは「2八」と「8二」といった具合に覚えやすいところから慣れていくのが良いでしょう。盤のど真ん中は「5五」です。そこを起点として覚えていくのも良いと思います。

持ち時間で考えているのは、基本的にはその局面での最善手。でも対局相手によって棋風が違うから、それを加味して指し手を選んだり読みの重点を変えることもありますよ。食事休憩の時間が近くなってきた時には、指し手を決めていても対局相手との駆け引きで休憩後に指すようにあえて持ち時間を使う事もあります。将棋は対人戦だから、相手より時間を多く使っていたり、あるいは相手が自分よりも多く時間を使っている場合には、その状況の応じて持ち時間の使い方が変わってくる事も多くありますよ。

局面によって違うけれど、100手くらいは読んでいますね。直線では30手ほどで、例えば候補手が3つあったとすればそれぞれを枝葉のように読み進めていくから、単純計算で100手近くは読んでいることになりますね。一局を左右するような難しい局面での長考では100手を超えて読むこともあります。でもこれは、プロ棋士のとっても高度なテクニック。将棋を覚えたての方やこれから将棋を強くなりたいという方は、自分の想像できる範囲をしっかりと考えるというのが大切ですね。無理に先を読むのではなく、最初は「3手の読み」(自分が指して、相手がこう来たら、自分はこう指す)の意識を持つだけでも良いと思いますよ。仮にその読みが外れてしまっても構いません。プロ棋士も長考して指したのに相手の対応が全くの予想外だったという事もあります。それも将棋の面白いところですね。

覚えていますね。ただ対局直後の感想戦では疲労によって細かな手順(主に序盤)の記憶があやふやになる場合も。対局が終わるとすぐに記録係から棋譜を渡されるので、それで手順を確認したり、持ち時間の使い方なども振り返りながら感想戦を進めていきます。感想戦自体を好きな棋士とあまり好きではない棋士がいますね。その対局で負けた棋士の意向によって決まる事が多いです。感想戦が長時間になったり、あるいは口頭だけで駒は動かさないで行う事や、まれに全く行われない事もありますよ。ちなみに私は感想戦はあまり好きではない方かもしれません。対局直後は疲労が大きいので早く家で休みたいなと思うこともしばしばです。

対局中、棋士は基本的には「正座」か「あぐら」。ずっと正座で対局に挑む棋士もいますが、私は足が痛くなってしまうので長時間の正座は苦手ですね。長考する時は「胡坐」でじっくりと読みを進めて、指す時に「正座」に座り直して指すという棋士が多いかもしれません。いずれにしろ対局は長時間座った状態ですので、腰や首を痛めてしまったという話もよく聞きますね。最近は棋戦によっては椅子席での対局も増えていて、その方がありがたいという棋士も多いと思いますよ。

将棋の研究をしたり趣味の時間にしたりといった感じで過ごすことが多いと思いますよ。私は、対局日以外にも将棋教室の講師やYouTubeの撮影編集といったお仕事をしている日もあります。他の棋士がどういったオフを過ごしているのか興味はあるけれど、棋士同士で普段のプライベートの話はあまりしないですね。ただ、対局の翌日だけはできるだけ予定を入れずに休養するという棋士が多いです。私も家でぐったりしている事が多いですよ。

棋士にとって書道は必修というわけではありませんが、習っている棋士も多いですね。将棋連盟には「書道部」があって月に一度のペースで活動していて、任意の部活ですが書道の先生を招いて書の指導を受けて腕を磨いたという棋士もいますよ。

棋士と言えば和服をイメージする人も多いけれど、普段の対局では大半の棋士がスーツで対局をしていて、タイトル戦や棋戦の決勝などの大舞台では和服を着用するというのが将棋界の習わしとなっていますね。最近では夏はクールビズの棋士も増えてきてるんですよ。また、対局の際に持っていく小物も棋士と言えば扇子ですが、それ以外にもいろいろあります。目薬は多くの棋士が持ってきていますし、他には休憩の時にホットアイマスクで目の疲れを取っている棋士もいますね。私は冬の対局ではカイロと毛布を持参していますよ。

私がプロ棋士になった頃(20年ほど前)と比べると、棋士が対局時に使用する扇子の種類が増えた気がしますね。昔は白扇子や棋士の揮毫が入ったものがほとんどでしたが、最近ではサイズも様々、模様もやや派手な染物からシックな色などたくさん見かけますよ。私もネットショッピングで京都の扇子を取り寄せて対局で使用していますね。特に制限などはありませんが、扇子の音を出し過ぎるとマナー違反になるので配慮は必要ですよ。

たくさんの対局をしてきましたが、今でも駒を並べる時や初手を指す時に武者震いをする事がありますよ。(私の経験ではそういった力の入りすぎも良くないです)また、対局の終盤戦で際どい勝負が続いた先で自分の勝ちが見えた時に手が思うように動かなくなるという経験も。ひたむきに最善手だけを追い求めていた時に突然意識する「勝利」が体をそうさせるのかもしれませんね。