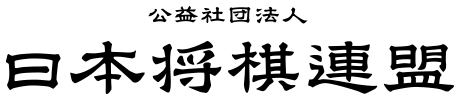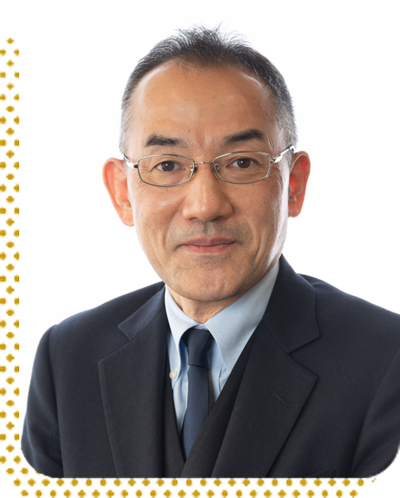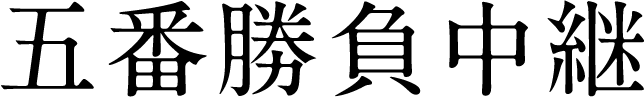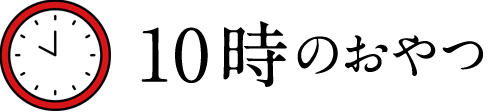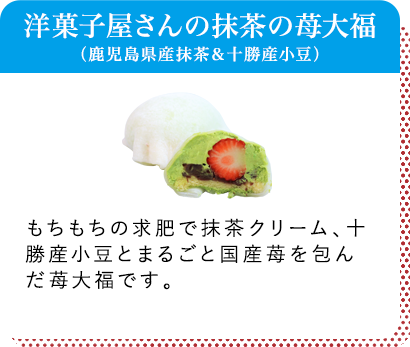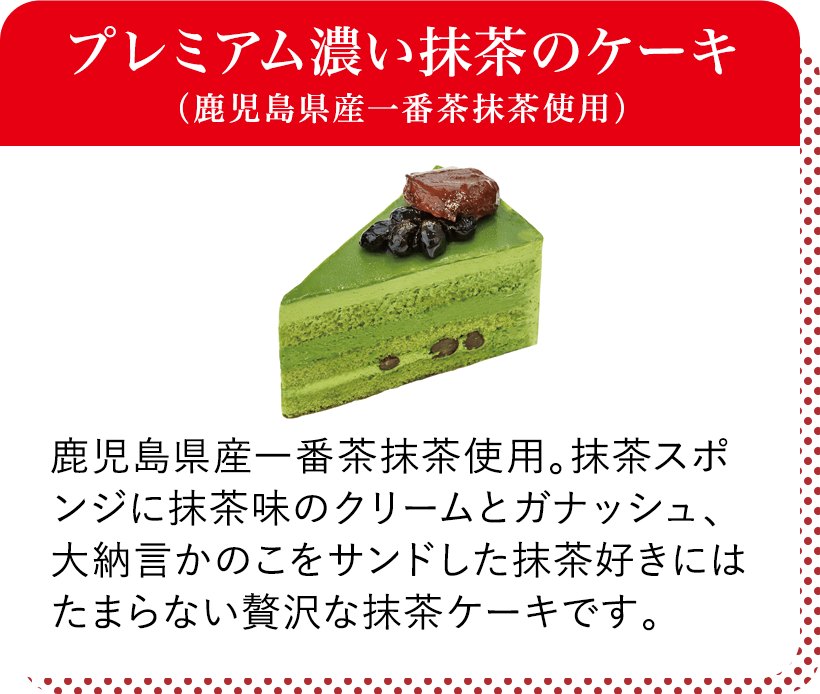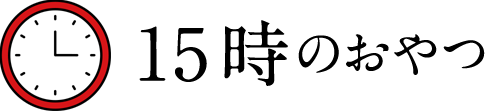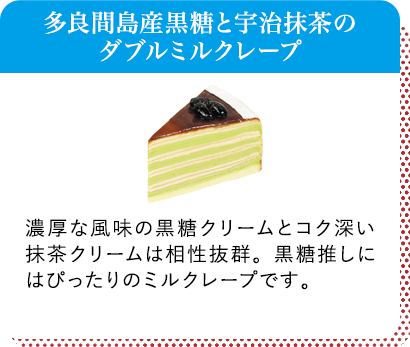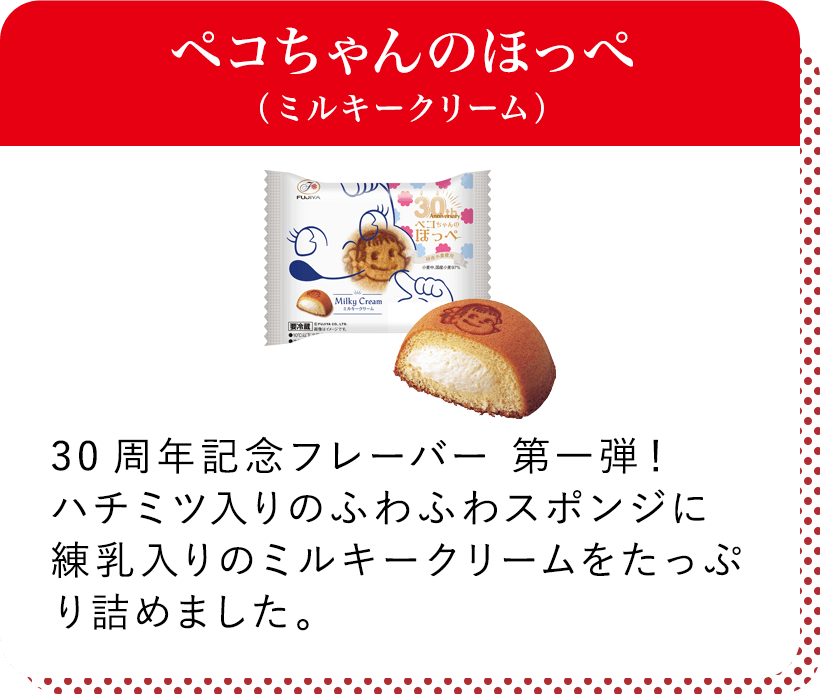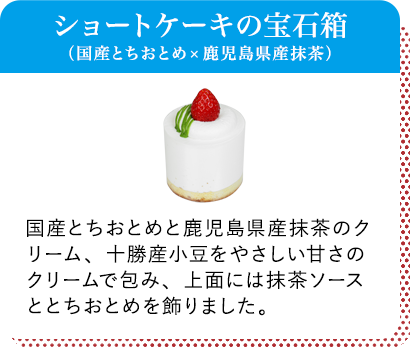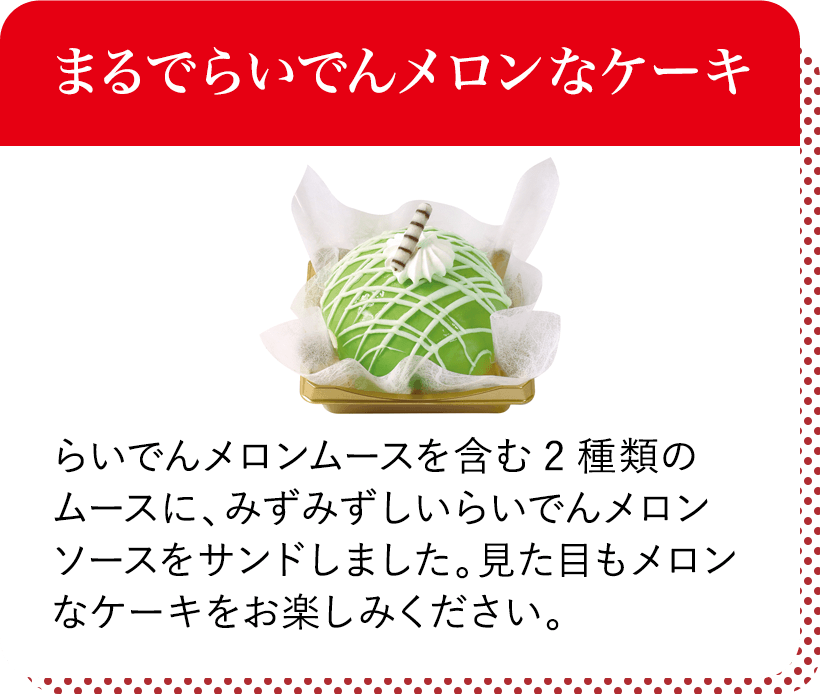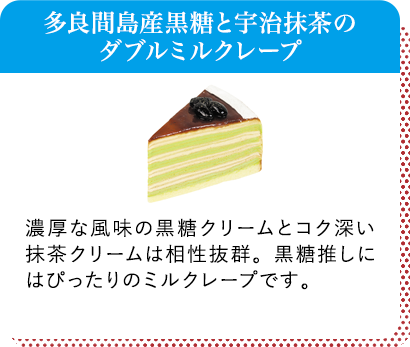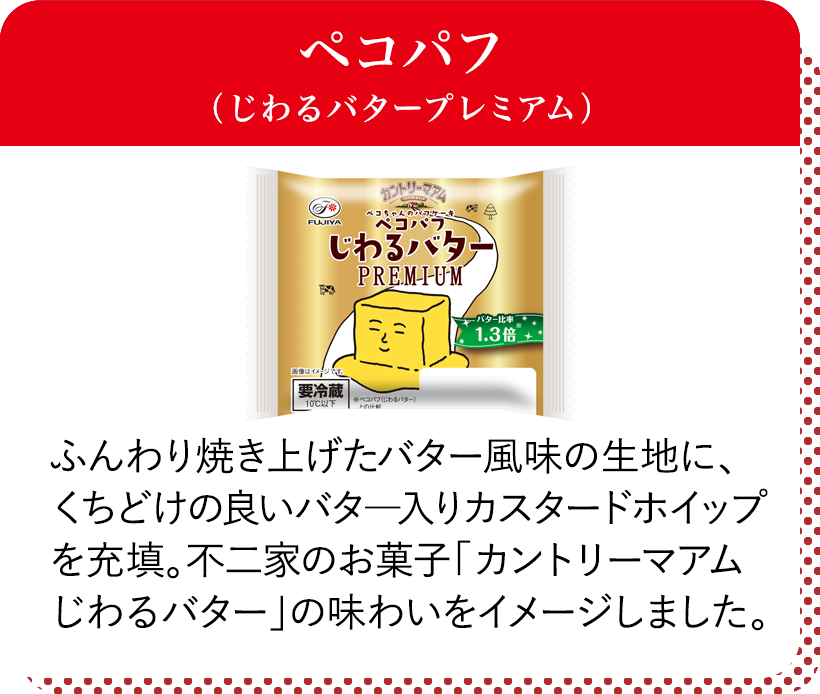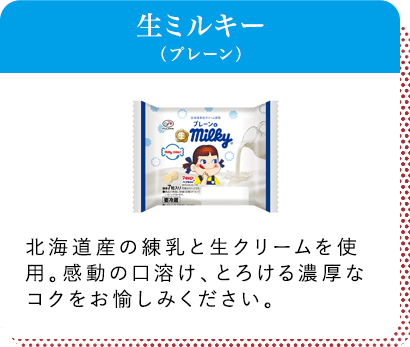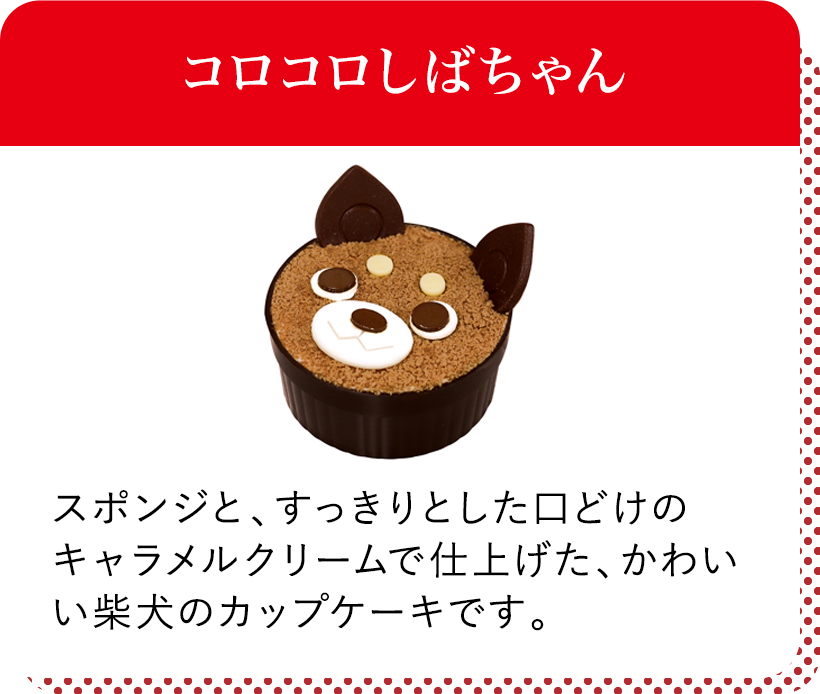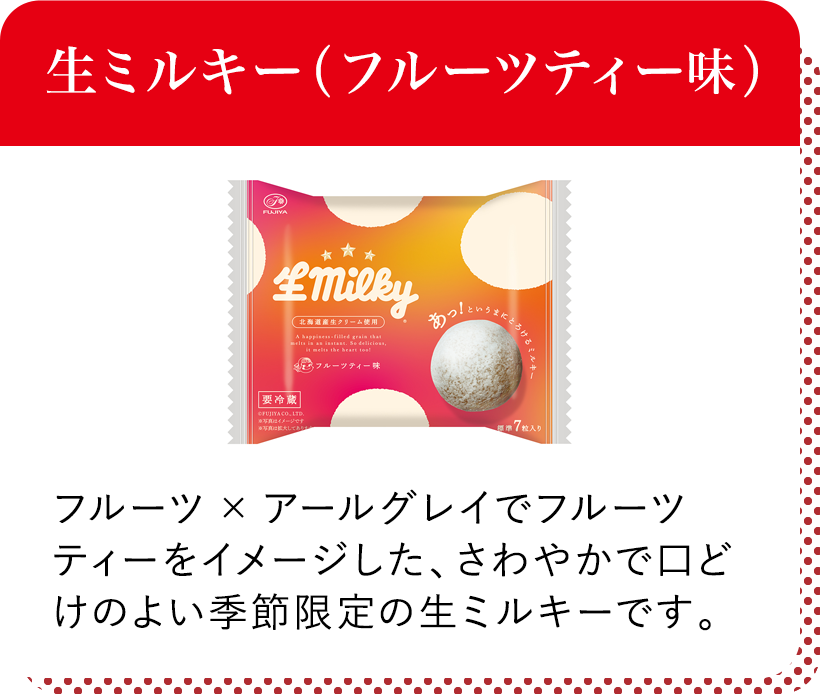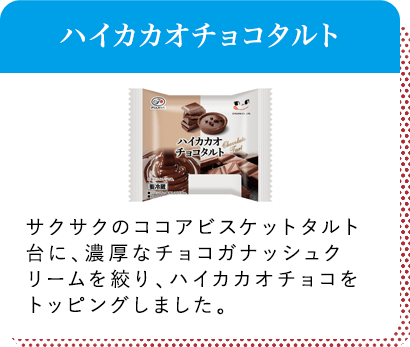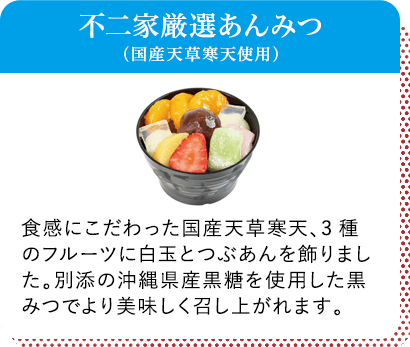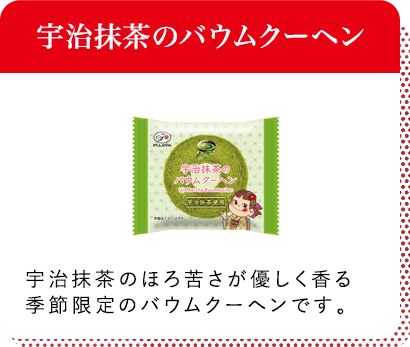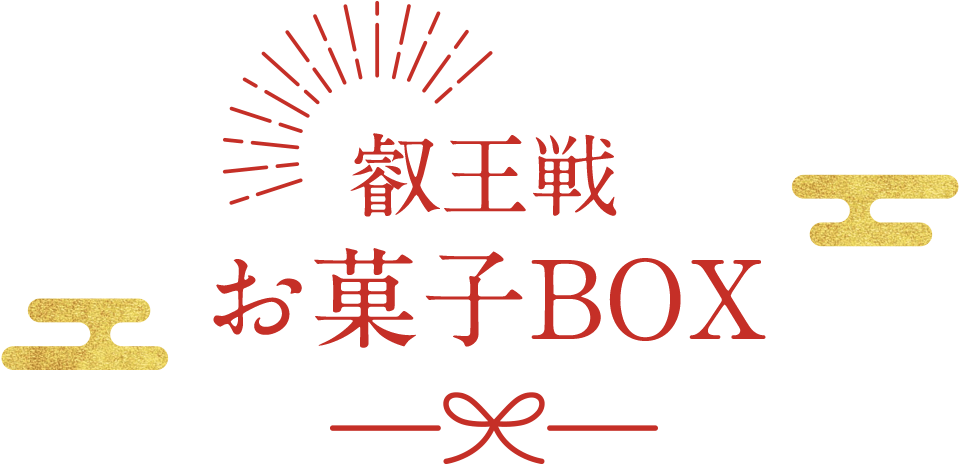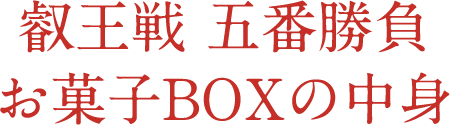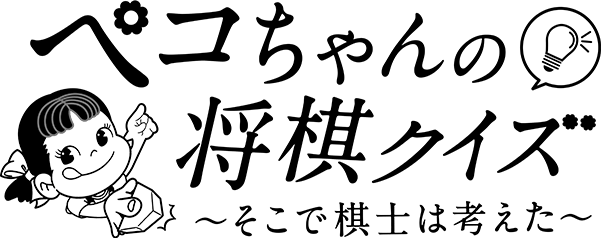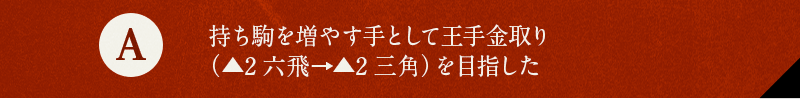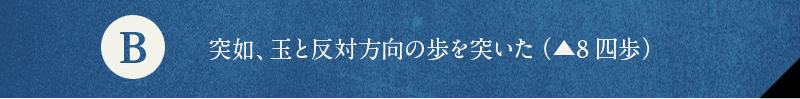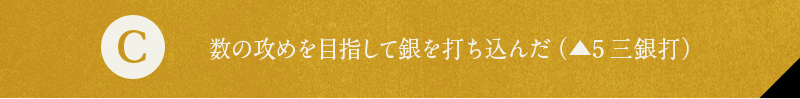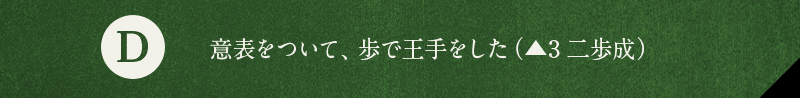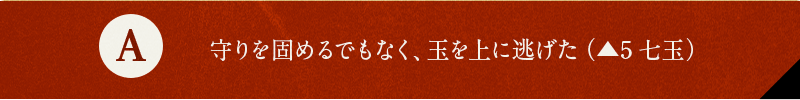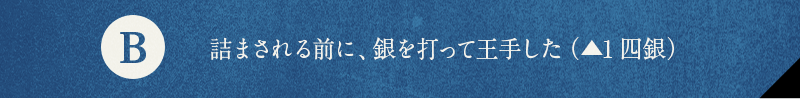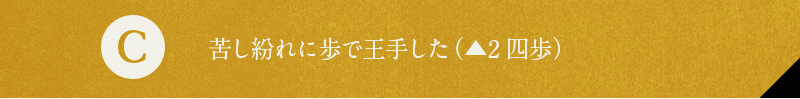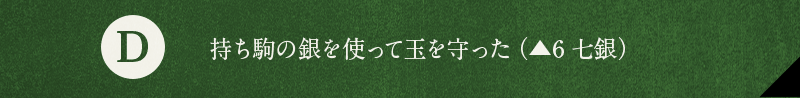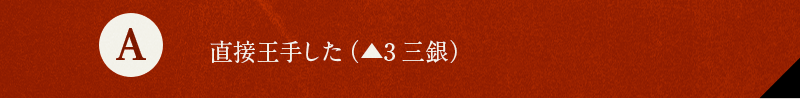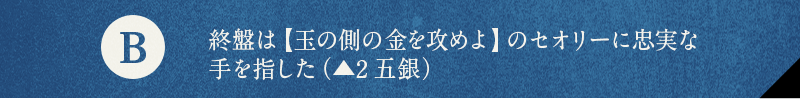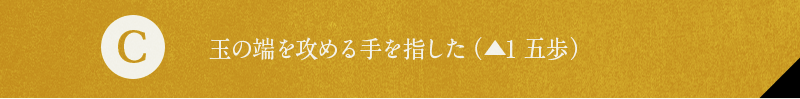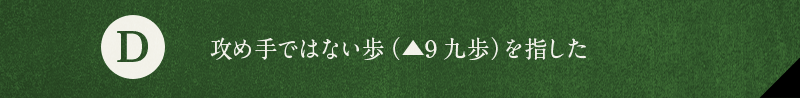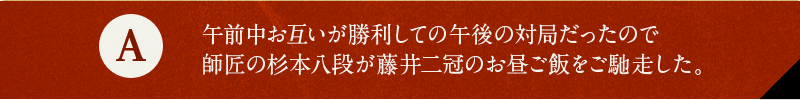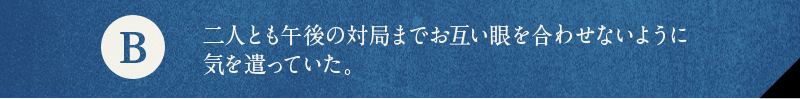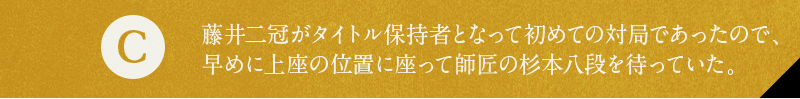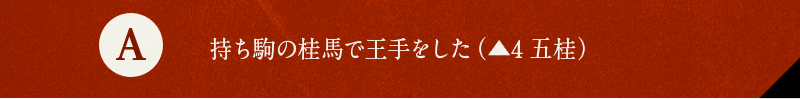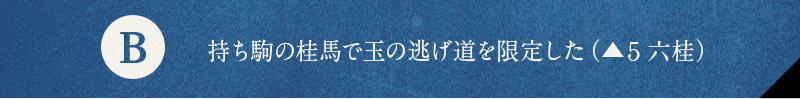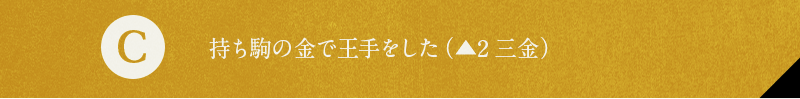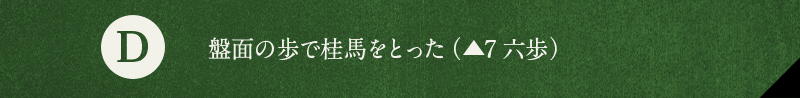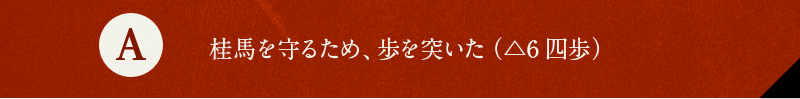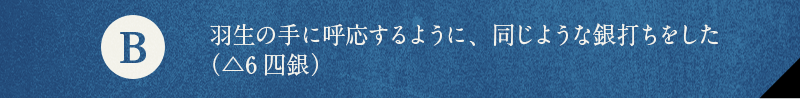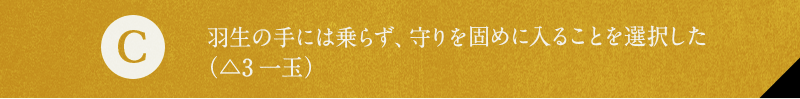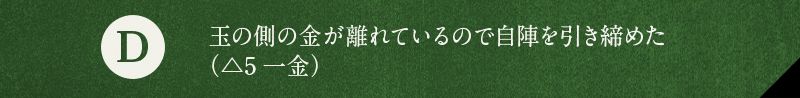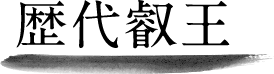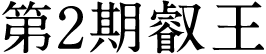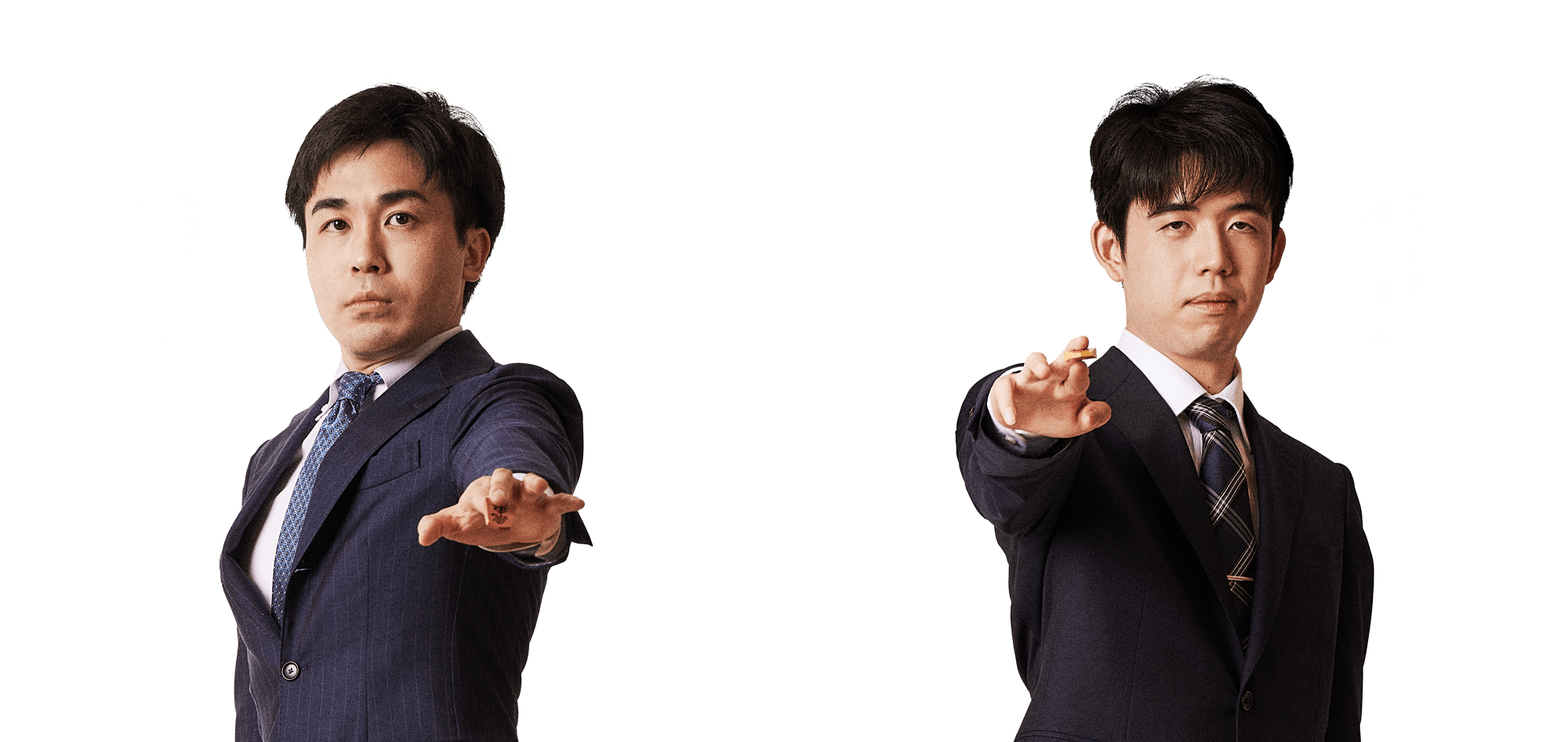


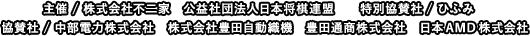
将棋のタイトル戦「叡王戦」で指された
スゴい一手を、やさしいクイズに。
将棋の知識がなくても、ちょっと
だけ棋士の気持ちになれるかも!
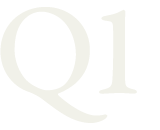
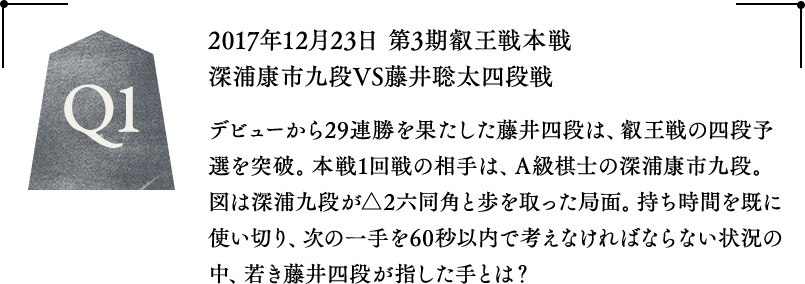


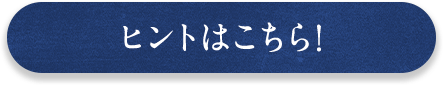
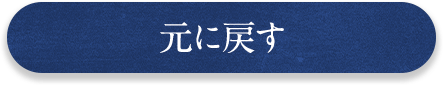
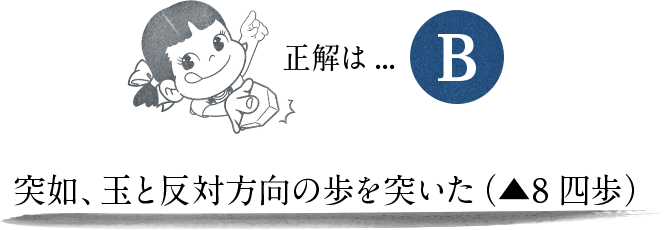
藤井四段の才能を示した「視野の広い手」
直感では王手金取り(▲2六飛△同銀▲2三角)を指したいところだが、この場面で藤井は玉と反対方向の歩を突いた(▲8四歩)。それは8二の地点を埋め、玉の退路を断ちにいった手。(もし▲8四歩を△同歩と取れば▲8二歩と指し、△同飛と指してくれればその地点が埋まって即詰みになる仕掛け)
一方、冒頭の王手金取りを選択して盤面を進めていくと玉に逃げられて詰まない(△5一玉▲3四角成とした後、△3六飛とされて、以下▲5二馬と王手をしても△7一玉~△8二玉と逃げられる)。いわば、深浦が誘い出した巧妙なおとりに食いつくような手だった。秒読みの状況でこの手を指した藤井の盤面を常に広く見ている眼に驚く。
ただ、さすがはA級棋士である深浦九段は藤井のこの手にしっかり対応。この後も難しい局面での攻防が続き、最後は深浦九段の粘りに藤井は屈する。藤井は惜敗したものの、この敗戦後、また連勝を積み上げて棋士として朝日杯初優勝をし、藤井四段から五段、六段へそして七段と一年で昇段をしていく。負けを次の結果に結びつける藤井将棋。叡王への原点の対局となった。
※段位・タイトル等は対局時の記載としています




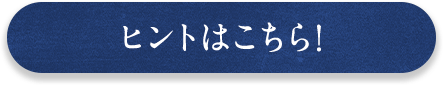
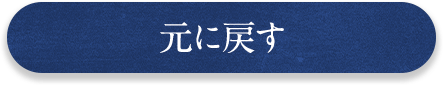

逃げただけに見えた手は、
一気に局面を打開する一手だった。藤井は▲5七玉と上に逃げた。優勢の小林は秒読みの中、飛車を成って(△7八飛成)、詰めろを続けた。しかし、その次に藤井が繰り出した一手は、飛車を成捨て、王手をかける驚きの一手(▲1三飛成)だった。小林はその飛車を歩でとる(△1三同歩)が、藤井は桂馬を打って王手をかけ(▲1五桂)即詰みに討ち取った。(※)不利な局面でも諦めずに粘り強く指し手を続けていく藤井将棋。藤井はこの第4期叡王戦は段位別予選で木下七段、この対局の小林(裕)七段、千葉七段に勝利し、本戦トーナメントに進出するが1回戦で斎藤慎太郎王座に敗れた。
(※)以下、△1四玉▲2六桂△2四玉▲2五歩△同玉▲1六銀△3六玉▲3七銀打とし5七の玉が4七の地点に利いているので即詰みとなる。
※段位・タイトル等は対局時の記載としています
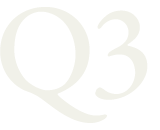
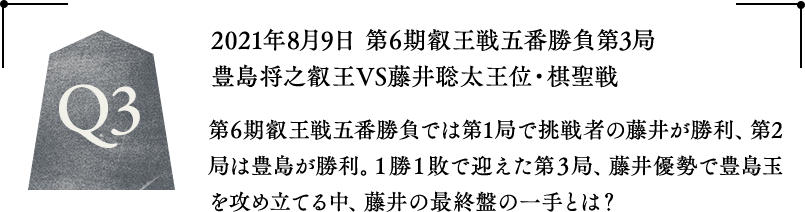


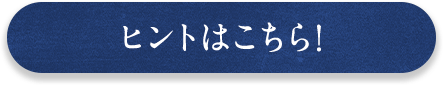
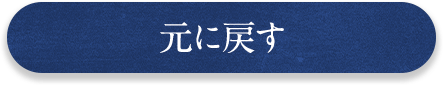

逆転の芽を摘んだ落ちつき払った一手藤井優勢で豊島を攻め立てる中、藤井は自陣の端っこ、豊島の馬の目の前に歩を打った(▲9九歩)。念には念を入れた一手に、控え室の棋士は「これは辛い勝ち方だ」と感嘆の声を上げた。その歩は何も守られておらず、ただただ豊島の馬にとらせるためだけの一手。歩をとらせることで馬をズラし、万が一にでも致命的な駒をとられて逆転をされないための念には念を入れた手に、仕方なく豊島は応じる。その後、3手進んで豊島が投了。相手の脅威を遠ざけ、逆転の芽を摘んでおき、あとはゆっくり追い詰めようという渋い一手で、藤井は三冠まであと1勝と迫った。 ※段位・タイトル等は対局時の記載としています
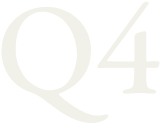
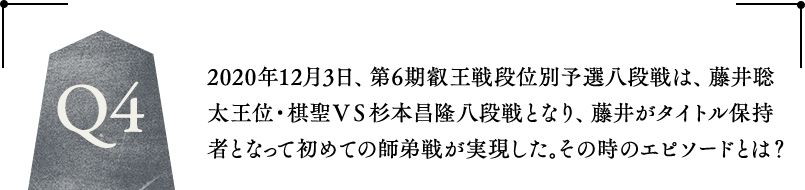

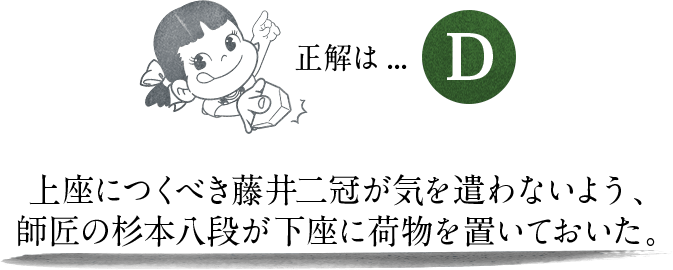
師匠の気遣いと、師匠への敬意。席次の規定は、二冠である藤井が上座であるものの、もしかすると藤井が師匠に気を遣って下座に着くかもしれないと考えた杉本八段。その日は30分以上も前から対局室に入った杉本は、自分の荷物をしっかりと下座に置き、上座をあけておいた。実際、その後、藤井は下座側から入室。だが、下座にしっかりと置かれた杉本の荷物を見て諦めたようで、上座に着いた。二人が席に着いた際、藤井二冠が「こちらで失礼をします」と深々と頭をさげた。杉本と藤井の師弟関係を顕す良い光景であった。 ※段位・タイトル等は対局時の記載としています

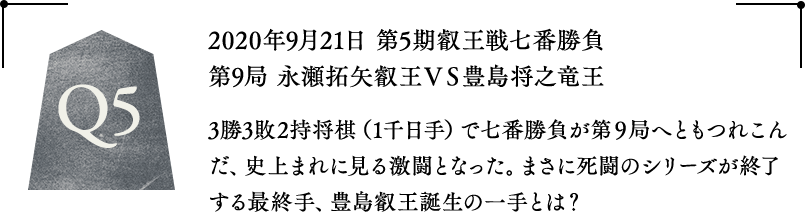


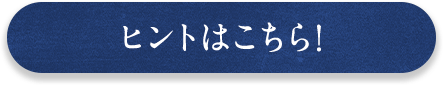
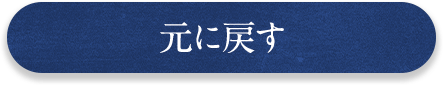

タイトル史上最多手数1418手を
記録した最後の一手
豊島は駒台から桂馬を打ち、王手をした(▲4五桂)。これに対して、玉が逃げる手はどれも金を打てば詰みなので、この時点で永瀬の投了となった。(△同馬と取るしかないが、それは8一の馬が利いているので▲同馬と取られて先手玉は詰まない)
タイトル史上総手数を更新し、何と1418手の激闘は終わった。A1技術が注目される将棋界であるが、二人の生の人間が繰り出す手の応酬を多くの人が堪能したシリーズとして記憶に残り続ける対局となった。
※段位・タイトル等は対局時の記載としています
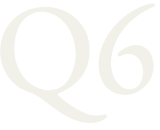



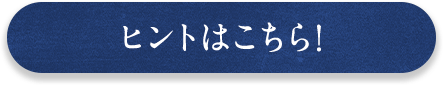
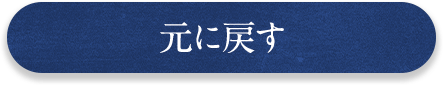
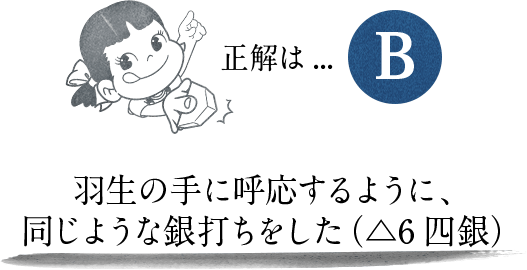
オールドファンも注目、往年の名カードが実現。 遡れば二人が小学生時代から盤を挟んで対峙し、138戦目となるこの対局に、多くのオールドファンが注目した。この場面、羽生の▲8六銀に呼応するかのように、森内も△6四銀と打ち返した。当時の記事でこの銀の打ち返しに「う~ん、いやぁ」と羽生が髪をかき上げて考慮を続けたと記されている。この仕草は羽生がよくタイトル戦でも見せる仕草だが、とても楽しそうに映る。将棋の対局は二人で築いていくもの。一人だけが良い手を続けていても相手がそれに対応していかなくては良い棋譜は生まれない。二人の阿吽の呼吸が、良いメロディーを奏でるように羽生と森内のベテランの音色が聞こえてきそうな局面である。叡王戦、特に九段戦、八段戦にオールドファンが注目するのは、ベテランならではの棋風がぶつかり合う音色(棋譜)が聞こえてくるからかもしれない。普段はなかなか見られない往年の名カードが実現するのも、段位別予選がある叡王戦ならではのおもしろさだ。 ※段位・タイトル等は対局時の記載としています